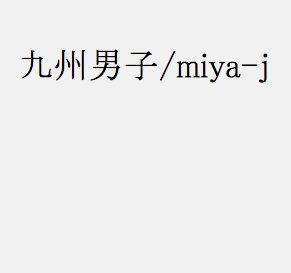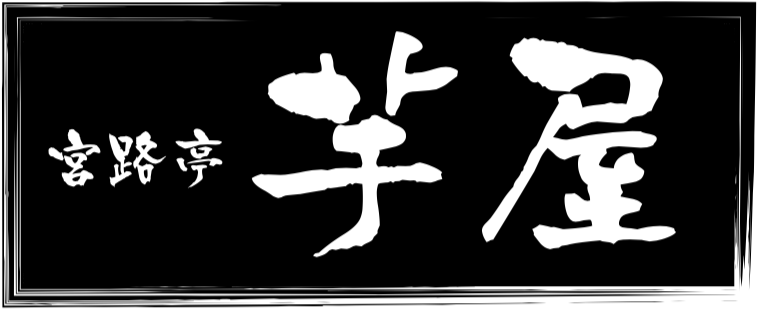先日、映画の「ジョーカー」を観た。
賛否両論ある本映画であるが(面白い!微妙~。に結構分かれる)
個人的には「シン・ゴジラ」に匹敵するぐらい久しぶりの超ヒット!!
そこで、下記noteに触発されて、面白いと思った感想をまとめてみたい。
(そこまでネタバレ感は強くないかな~と思います)
裏側知ってるほうが楽しめる#2
映画の内容としては、
「バットマン」に登場する最強の悪役ジョーカーを主役にすえ、
メガサイコパスと言える「ジョーカー」が誕生するまでを描いた映画。
大道芸人であった主人公が、様々な悲劇にあい、悪へと変貌し、
混乱をきたす社会情勢の中、悪のカリスマになっていくストーリーである。
僕が個人的に面白いと感じたポイントは、
「正義・正解・正しい・善・面白いの答えは一つでは無い」という観点だ。
イメージとしては、
「Aという見方のヒトからすると、正義はAであり、Bは悪である」
「Bという見方のヒトからすると、正義はBであり、Aは悪である」
では正義とは何か?と問われたら
「自分で正義の定義を決めて、それを信じるしか無い」
という考え方である。
ジョーカーを観ていて、
主人公の正義と面白いの定義が、周りに受け入れて貰えない不遇を経験し、
再構築されて行く様に、上記の考え方をリンクさせて非常に面白く感じたのだと思う。
また、最後に「君はそれを面白いと思っているのかね!?」的な問答があるのだが、
まさに、そこの切り返しなどが非常にグッと来たポイントである。
そして、そんなストーリーを演じる演技力や演出が最高に鳥肌がたった。
さて、なんでそんなポイントを面白いと感じたのかという個人的な所感。
僕は、正義も悪も、正しいも間違いも、自分で決めたいのだ。
なんでそんな風に思うようになったのかは、探ってみたが不明である。
例えば、こんなエピソードがある。
小学2年生の頃に作文の授業があった。
コンクールに出す作文だったがテーマは自由だったと思う。
僕は「なぜ、ラーメンを待つ3分は長く感じて、友人と遊ぶ3分は短く感じるのか?」
というテーマを作文に書いて提出したのを覚えている。
しかし提出した所、先生に出し直しを命じられた。
表現が分かりにくかったのかと思い、書き直して再提出したけど駄目だった。
今、思うと立派な心理学にある「時間感覚」の研究テーマであるし、
ひいては相対性理論に通じるような気さえする(笑)
なんか、自分が良いと思ったモノが、
よく分からないモヤッとした価値観に否定される感覚が嫌いなのだ。
僕は、自分が納得できないモヤッとしたモノが嫌いなのだ。
更にモヤッとしたものに迎合していく様が、気色悪いのだ。
先日、大学院の中で倫理観に関するクラスがあったが、
「あなたの倫理観は10段階のうち、どのくらい?」と問われ、「2段階」と答えた。
言語化できてないモヤッと中に浮いた倫理観を共通認識することが出来ないし、
誰かが決めたモノに合わせる気は無いのだ。
「歴史の背景を理解するためなのに、語呂合わせで覚えるのが気に食わない」
「英語の授業なのに、関係代名詞という国語が使われているのが気に食わない」
「目に見えないヒトに募金はしないが、
目の前の困っているヒトが居たら、一瞬も迷わず手を差し伸べる」
そんな感じで、自分が正しいと思ったモノを軸にして生きたいのだ。
誰が決めたか分からないモヤッとした正義に、自分の価値観を置きたくない。
日本は、テレビヒーローの正義は一つだし、正解教育であると感じる。
メディアや教育によって、「正解・正義・面白い」はモヤッと一つにされている。
大人になってビジネスを初めて、「正解・正義は一つでは無い」と感じた事は無いか?
そんなとき、「自分は◯◯という理由によりコレが正しい選択だと思う」
という発言が出来る事は大きな価値があるような気がするこの頃である。
ヒトに受け入れられるモノで無いと売れない。
ヒトが笑わないと面白いとは認知されない。
確かにその通りだが、それはセグメンテーションやターゲティングの話であって、
そのボリュームゾーンを狙いたいなら、狙ってやればいいと思うのだ。
寂しい時は、皆というモヤッとしたモノに合わせればいいが、
自分で人生を選択する時などは、モヤッとしたナニカに振り回されたくない。
そして、
自分の価値観に基づき、正解・正義を判断するとした時に、自分の価値観が必要になる。
自分の辞書を作るかのように「自分の哲学(価値観)を持て」と思うのである。